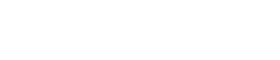『一橋ビジネスレビュー』の今(+研究会趣旨説明・質疑応答)
オンライン研究会「大学が学術出版をする意義と方向性(1)」2023/02/03
研究・イノベーション学会 大学経営研究懇談会
https://kiyo.cseas.kyoto-u.ac.jp/2023/03/seminar2023-02-03/
〈研究会趣旨説明〉
原田隆(東京工業大学 主任リサーチ・アドミニストレーター)
研究・イノベーション学会、大学経営研究懇談会の幹事をしています原田と申します。本オンライン研究会は紀要編集者ネットワークと共催で開催いたします。
研究イノベーション学会の中において、われわれ懇談会は大学経営の観点から大学評価、研究評価や研究インテグリティなどについて継続的な研究報告をしています。今年度については、大学が出版をする意義について定期的に扱っていきたいと思っています。例えば、国際ジャーナルへの投稿などが推奨され、それが評価されるなか、日本語論文の投稿の問題があります。また、いろいろな媒体で動画などを含めいろいろな形で研究成果が発信されていくなか、紀要が代表的ですが、あえて大学が出版機能を持つ社会的意義はなんでしょうか。もし本質的に大学が研究出版機能を持つべきであるならば、どのようにしてそれを大学経営の中に位置づけるか、もしくはそのために何を犠牲にするかというようなことを考えていきたいと思っています。
これまで紀要、日本の学術誌について継続して研究会を開催していますが、今回は『一橋ビジネスレビュー』を題材にして、この点を考えていきたいと思っています。講師は一橋大学の吉岡先生にお願いしました。『一橋ビジネスレビュー』については、講演で詳細が述べられますけども、一橋大学の出版物ですが商業誌として発行されている紀要です。ただ、これが紀要の定義として適切かどうかということも議論だと思っています。
〈講演〉
吉岡(小林)徹(一橋大学 イノベーション研究センター)
一橋大学イノベーション研究センターの吉岡と申します。よろしくお願いいたします。今日は、『一橋ビジネスレビュー』が今どうなっているか、大学として出版機能の一部分を担って本を出していくなかでどういうところが悩みかをお話したいと思います。まず『一橋ビジネスレビュー』にどういう経緯があったか、そして今どうなっているか、理想としてはこうありたい姿、最後に悩みという形でお話を進めていきます。
その前に、私の立ち位置のご紹介ですが、元々は法律の研究をやっており、民間を経て、大学の教員をしています。専門分野は科学技術政策や技術マネジメントで、研究成果を主に海外の学術誌で出していきたいという意欲を持っていますが、必ずしもうまくいかないという感じですね。
『一橋ビジネスレビュー』の昔
早速ですが、『一橋ビジネスレビュー』の昔について話します。まず、『一橋ビジネスレビュー』が紐づいている、私の所属機関である一橋大学のイノベーション研究センターについて簡単にご紹介します。発足は戦争中の1944年でした。その後、1949年に産業経営研究所、つまり産業の経営に関わることを研究していく機関となり、その4年後の1953年に『ビジネスレビュー』を一般向けに経営学の内容を伝えていく雑誌として創刊しました。ですから、歴史はとても長く、今年70年になろうとしています。ただ、東洋経済新報社から季節ごとに刊行する季刊の本として出したのが2000年で、このときに『一橋ビジネスレビュー』と名前を変えました。
一般の紀要と異なり、出版元は東洋経済新報社です。東洋経済新報社がちゃんとお金を取って、書店を通じて売っています。
理念は、理論と実務を繋ぐ架け橋として経営学に寄与することです。ここからおわかりの通り、ターゲットは産業界の方、実務家の方で、顧客価値は経営学の理念を実務に活かしてもらう、実務のヒントを得てもらうところにあります。後ほど詳細をお話しします。
『一橋ビジネスレビュー』の今——雑誌の概要——
今はどうなっているかといいますと、4か月に1回発行して、1号2200円です。内容は、特集記事としてテーマ——最新号(2022年度Vol.70 No.3)だと「デザインとは何か?」というテーマ——に沿った記事を5から7本、連載——主に経営学の解説——を1、2本、インタビュー記事を1本、そしてケーススタディ、この企業がこんな取り組みをしているとか、こういうところが面白いというのを1、2本。厳密な意味の研究論文が特集記事に含まれることがあるんですけれども、それを除くとまれに1本載る程度です。
ですので、一般的な学術紀要ではなく、どちらかというとビジネス誌になります。ただ、ビジネス誌としても東洋経済新報社が発行している『東洋経済』や『週刊ダイヤモンド』などに比べると、学術的なバックグラウンドが重視されているという立ち位置にあります。完璧なビジネス誌と学術誌のちょうど中間点ぐらいのものを目指しているのが、この『一橋ビジネスレビュー』です。『ハーバード・ビジネス・レビュー』が一つのお手本といえると捉えています。
『一橋ビジネスレビュー』の今——記事の例——
記事はこんな感じです。抽象的に話してもわかりにくいと思いますので、最新の号の「デザインとは何か?」の中身を書きました。特集記事のテーマは、過去の例では2021年に「研究力の危機を乗り越える」を取り上げるなど、その時々に応じた話題を選択しています。最新号の特集記事を書いてもらった永井一史さんはグッドデザイン賞の審査委員長で実務家、森永先生、木見田先生、古江先生は研究者、山中先生はちょうどその中間、実務と学術を両方やっている方です。連載では、エフェクチュエーションって何なんだろうか、イノベーション・マネジメントは何が基本なんだろうかといった話を取り上げています。それから、衛星宇宙開発ビジネスについてインタビューしたり、旭酒造さんやログハウスメーカーのビジネスケースを書いたりしています。
こういった内容で、ビジネス向けの雑誌なんですけれども、学術的なバックグラウンドを保っているところが、『一橋ビジネスレビュー』の特徴だと思います。
『一橋ビジネスレビュー』の今——企画・編集体制——
編集・企画は、基本的には研究者でやっています。一橋大学イノベーション研究センターのセンター長だった米倉誠一郎先生を編集長として、その他センター所属の教員9名が関わっていますし、さらに経営管理研究科のイノベーション系の研究者も数名関わっています。15名ぐらいで企画している体制です。
東洋経済新報社の担当編集者も入っています。プロの編集者の介入はクオリティコントロールにすごく大事なところです。その方が、この企画はつまらないですねとか、個別の記事にもこんな書き方だと駄目ですよと厳しく言ってくれる体制です。
ただ、ロジ回りまで東洋経済新報社に完全に任せるのは無理なので、私どものセンターの助手に執筆者の対応や原稿関係の細かいところを担当してもらい、編集、そして校正の段階を東洋経済新報社の方にやっていただいています。
『一橋ビジネスレビュー』の今——経営学内の傾向と一橋ビジネスレビューの位置づけ——
内部的な話をすると、各研究者の研究の立ち位置は、経営学では大きく三つの切り口で特徴づけられるんですね。1番目の軸は、理論を重視するのか、実証を重視するのか、それとも現状を記述することを重視するのか。2番目の軸は、定性的なアプローチ、つまりインタビューや一次資料をベースに考えていくのか、それとも操作化をして、数字に変えて定量的に分析をしていくのか。3番目の軸が、実務で貢献するのか、学術で貢献するのか。この掛け算でだいたい各研究者の立ち位置が決まっています。
『一橋ビジネスレビュー』はビジネスレビューですので、当然好まれるのは最終的な実務への貢献なんですね。実務で貢献すればいいので、場合によっては、記述さえしておけばいい、面白い現象を切り取っておけばいいんですけど、悩ましいところは各メンバーとしては学術にも貢献したいという思いが強いんですね。そうなると、理論か実証をやりたくなる。ただ、実証をやると個々の論文としては実務への貢献が小さくなるというジレンマがあって、企画メンバー全員が『一橋ビジネスレビュー』に対して必ずしも強いコミットメントをしやすいわけではありません。
理想像——ターゲット層と顧客価値——
次は、お客様への価値、社会的な価値をお話すると、ターゲット層は基本的には経営者の方、それからミドル以上のマネージャー層の方、いわゆる部長職以上の方、あるいは将来部長それから役員になっていくような方々が潜在的な顧客層だと捉えています。
ただ、国勢調査のデータから考えると、日本の中でターゲット層となり得る最大の数がだいたい500万人ぐらいなんです。その中で学術的なものに関心があって、かつ学び続けたいという意欲を持っていて、しかも本当に学ぼうとする行動を取っている方となると、たぶん多くて100万人、実質は50万人、肌感覚ではもっと少ないかもしれないと思っています。
顧客価値として目指すのは、経営の知的レベルを向上させることです。ただし、知的能力のうち短期的な情報やノウハウではなく、普遍性が高いところをお伝えしようというのが僕らが一番目指すところです。季刊にしている説明は、読者に3か月をかけてじっくりと読みこなしてほしいということです。
学術コミュニティにおける位置づけとしては、アウトリーチの活動になると思っています。学術コミュニティへの貢献にはあんまりウエイトを置いていないんですね。ただ、社会に伝えることで学術コミュニティに返ってくるものがあると思っていますので、それは後ほどお話したいと思います。
企業は人を育てないし、半数の従業員は自発的に学ばない
大きな悩みの予告になるんですけど、実質的な顧客層が少なくなってきています。経産省があおるために作った資料と言ってもいいのかなと思いますが、「未来人材ビジョン」で、日本の企業はあまり人を育てていないし、従業員もあまり自分で学んでいないことが問題として指摘されています。私自身も民間にいたので、肌感覚としてそうだよねと。どこの会社でもというわけではなく、組織による差が大きいなと思っています。いずれにせよ、学ぼうという意欲を持っている方は、たぶんビジネスパーソンの中で10%、20%だろうな、そういう意味で顧客層は少ないんだろうなと捉えています。
理想像——書き手としての大学研究者への価値——
先ほど少しお話した学術コミュニティへの価値ですけれども、一つ大きい話をさせてください。私どもは社会科学をやっているわけで、社会を分析してそこから何か知見を得てということなんですが、社会科学の研究活動にはループがあるんじゃないかなと捉えています。
まず社会をどうやって眺めるんだろうか、人間の普遍の行動って何だろうかと理論を考える人たちがいて、その人たちが土なんですね。その土の上に、その理論が正しいのかを補強する実証の研究者が種を蒔いていって、その種が育っていく、芽が育っていくわけですね。芽が育っていくと、1個1個できあがっていた理論が体系化されて、それによって体系的な知識が編み上がる。その体系的な知識を社会に伝える人がいて、社会に伝えたことで、社会から体系的知識があったからこんなことがわかった、でもまだわからないところがあるよと反応がくることで、新しい理論研究や実証研究の種が生まれてくる。そういう循環があるんじゃないかなと思っています。
自分たちの研究成果を社会にいったん問うて、そうすると社会から反応が返ってくるわけです。あるいは私たちのフィールド使ってくださいって返ってくるわけですね。そういうのに繋がっていけばいいなと思っています。『一橋ビジネスレビュー』は、まさに社会に伝える役目によって、社会からこういう研究してみたらどうですかとか、こういうところが悩みなんですってフィードバックをもらう機会だと捉えています。これがある種の学術コミュニティへの価値なんじゃないかなと思っています。
もう一つ、細かいとこですけども、将来の実務家あるいは将来の研究者を育てるための素材として、教材として使ってほしい。このあたりが書き手の立場としての価値です。
単にアウトリーチということじゃなくて、教育の材料にもなるし、それによって関心を持ってもらって、企業さんからこんなデータを使っていいですよとか、うちの企業対象にやって分析していただいていいですよって言ってもらえるといいなと考えてやっています。
ターゲット層からの反応
ターゲット層からどれぐらい反応があるかですが、われわれの強力なコンペティターである『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』が2万部あるところ、私どもはさすがにそこまでではありません。私の調べ方が悪かったのかもしれませんが、苦しいのは図書館がほぼ買ってくれていないんですね[注:再調査の結果、200程度の大学図書館が購読継続中と判明(https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA11479006#anc-library)]。一橋ビジネスレビューは書籍としての位置づけであり、雑誌ではないので、公立図書館にとっては定期購読の対象として買いにくいのかもしれません。
こたえるのは、Twitterでの反応ですね。見ると、毎号ほぼ数件程度なんですね。『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』は、少なくとも毎号2,30件あるんですよ。苦しいなというのが正直なとこです。
悩み①——理念に沿った記事を書ける人が限られている——
次に悩みは、今の話と重なるところと重ならないところがあります。まず重ならないところでは、誰が書けるのかという問題があります。
われわれの理念としては、普遍性の高いもの、3か月で読み解いてもらうような骨太の経営の本質を捉えた、あるいは経営者にとってそれを知っておくことがすごく有益な情報を提供することを目指したいわけです。逆に言うと、短期的な話は『週刊ダイヤモンド』や『東洋経済』に任せるということを明確にしています。そういった理念に沿ったものを1記事だいたい1万5千字書かなくちゃいけない。
書くって大変なんですよ。研究者でも論文を書ける人は限られています。社会科学では、査読付きにせよ査読付きに近いクオリティの論文にせよ年間1本書いている方は全体の10%ぐらいかなという気がします。ごくわずかな人が多数の論文や書籍を出しているのが実態です。ただ、社会科学では日本に限らず、世界的にもロトカの法則なんて言われたりするんですよね。ざっくり言うと、2割の人が8割の成果を出すといった話です。
さらに、研究者としてやり込んでいる方が実務家にわかりやすく書けるかというと難しいんですね。ただ、私どもの経営学分野にはビジネススクールがありますので、そちらの教員の方だとすごく上手いんですが、純粋に研究だけされている方ですとつらいところもあります。
実務家の方だと書けるのかというと、これもまたかなり厳しいです。行政官の方は、いろんなファクトをご存知で面白いんですけれど、ポンチ絵の文化があって一貫性のある長い文章を必ずしも書く機会が多いわけではないので、1個1個の3000字ぐらいの塊としてはすごく面白いんですが、1万5千字書いたときに5つのバラバラな話がある形になることがあります。実務家の方も同じで、1ページに要約して箇条書きで書くことに慣れていらっしゃるので、キーワードは面白いんですけども、ロジックの繋がりがないのが目立ってしまうことがあります。
実務家の方にお願いするときは、それなりに編集者の手が入らないと厳しいというのが実態ですし、企画時にこういう内容でどうですかと綿密な打ち合わせをして詰めていくことが多いです。もちろん例外もあって、実務の方でもすごく面白い文章を書ける方もいらっしゃいます。とくに行政官の方がそうです。そういう方をいかにうまく繋がりの中で見つけ出すかが勝負になっています。
悩み②——大学に対する規範的要請、政策的要請——
書き手の半分ぐらいは研究者ですので、大学の研究者の側から今の状況を見ると、当然若手にはいかに論文をたくさん書くかという意識があります。ただ、publish or perish、書かないとクビになるぞみたいな話は日本だとそこまでないんですよ。なぜかというと、経営学では博士課程の修了生に比べて教員枠の空きがあります。これはクオリティのある博士課程の修了生に比べると教員枠が大きいという意味ですよ。だから、そんなに論文を頑張って書かなくてもいいんですが、そうは言っても書いてないと駄目だよねという認識が僕らの中で共有されてきています。
もう一つ、私ども個別の事情ですけれども、一橋大学は指定国立大学法人になって、英文査読付き論文を書きましょうという要請があります。現状厳しいところもありますが、英文査読付き論文を書いて、しかも引用された数が多いと給与が増える状況です。
さらに、部局レベルでも、イノベーション研究センターが所属しているのが経営管理研究科、商学部で、そちらがビジネススクールとしての国際認証を受けるようになりましたので、国際基準として英文査読付き論文を書かなくちゃいけないんです。ただし、5年に1本でいいですし、あんまり高い質じゃなくてもいい。海外トップジャーナルに載せろという話ではないんですね。国際的なビジネススクールの認証はバランスが取れていて、ビジネススクールなんだから論文への貢献、学術コミュニティへの貢献ばっかりしていてもしょうがないと書いてあるわけですよ。この点からすれば、英文査読付き論文を書く強い要請があるわけじゃないんです。
そうは言っても、とくに若手の認識は、経営学の研究はアメリカ、ヨーロッパ全般、中国、インド、韓国、台湾で活発に研究が積み重ねられている、それにキャッチアップしたい、自分たちも発信をしないといけない、英文の査読付き論文が大事なんじゃないかといったところだろうと思います。ただ、英文査読付き論文を書くのはすごく大変なんですね。1本書き上げて、査読を頑張って通すのに、1000時間とか1500時間とか投入していることもあるかもしれません。そうなると、実務家に貢献するアウトリーチの記事を書く時間はどうしても削られるんですよ。そこが研究者の立場としては大きな悩みです。
総論としての悩み——社会科学分野での特定大学の学術誌の立ち位置の難しさ——
最後に、大学レベル、部局レベルの経営目線の話をしてまとめにしたいと思います。社会科学分野で、大学としてあるいは部局として学術誌を持つ立ち位置の難しさがあります。
研究成果のアウトリーチなら、とくに社会科学だったら、書籍を書いた方が本当はいいわけです。そういう意味では、ビジネス誌は中途半端であるかもしれません。ただ、唯一の救いは、書籍を書くのはすごく大変ですが、書籍を書けるレベルの、しかも一般に受けるような書籍を書けるのかどうかのテストの場として、この『一橋ビジネスレビュー』が機能しています。ただ、他のインターネット記事、『東洋経済オンライン』や『プレジデントオンライン』、noteやブログに負けかねないところがあって、そこは悩みです。編集者さんが入って、しかも企画の目が入って、クオリティコントロールがされて、トレーニングの場があるところが一つの価値かなと思います。ただ非常に脆弱な価値である可能性が残されています。
研究成果発表の場だったら、当然海外の査読付き論文にした方がいいわけですし、しかも、海外査読付き論文誌は今無数に出ています。経営学のそこそこのクオリティのものだけでも、たぶん100誌とかあるわけです。だから、変なことを書いてもけっこう通るわけですよ。国内学術誌よりも通りやすい場合もあるわけです。国内学術誌の方がよっぽどまともな査読をしているケースもあります。さらにいうと、プリントサーバーもあって、それでも十分というところです。だから、研究成果発表の場としては苦しい立ち位置にあると思っています。
若手育成の場だったら、国内学術誌が、とくに社会科学ですとその役割を頑張っています。一橋大学の商学部として紀要を持っていまして、そちらは院生のためのものとして機能はしているんですが、指導教員の立場としてはそれより学会で発表して、ドクトラル・コンソーシアムに出てもらうことをより意識しています。ドクトラル・コンソーシアムという博士が論文を書くためのトレーニングの特別な場があるんですね。しかも、海外学術誌や海外学会の方がこのような活動に熱心な場合もあります。
だから、私どもの分野だったら、学内誌としてはアウトリーチで勝負するしかないというのが実態です。
総論としての悩み——限られた資源をどう配分するか?——
これもやはり経営者目線での悩みは、資源が限られていることです。教員も事務職も支援の方々もみんな時間がないなかで、どう時間を配分すれば投下した時間に対して得られるリターンが大きいのかを意識しなくちゃいけないわけです。とくに注意しなくちゃいけないのは、苦しくなってくるとみんな新しいことやろうとするんですね。実はそういう研究があります。問題が起こって困ったときに人はどういう行動をとるかというと、基本的に解決策というか新しいことを足していくんです。足していくとどうなるかというと、忙しいので質が下がって、さらに悪くなっていく悪循環に陥るんですね。アウトリーチ活動もそうですし、学術誌を出すことがそうなりがちなところがあって、そこが悩みではあります。
私からの話題提供は以上ですが、最後に参考までにご紹介します。お客様への価値は実際どれぐらい伝わっているのか、『一橋ビジネスレビュー』のデータはお見せできないので、研究イノベーション学会の学術誌『研究技術計画』のダウンロード数を公表データから頑張って集計しました。
「研究ノート」や「研究論文」は研究者による査読付き論文、ビジネスレポートを除くと、それ以外は特集論文という企画意図を持って集めた原稿です。『一橋ビジネスレビュー』よりもうちょっと学術論文寄りですが、ほぼ同じような立ち位置です。研究者、大学の実務家、企業の実務家によるものがあります。ダウンロード数が多いのは基本的に、研究者の手による論文、しかも特集記事ですね。時代を捉えたもので、かつ俯瞰的なレビュー的なものが比較的ダウンロードされやすく、読んでもらいやすい。2020年、その次の年も、前の年もそうでした。この年は実は実務家の方の原稿が上がってきませんでした。高橋先生と私が書いた論文がトップで、その他はやっぱりレビュー系ですね、あるいはEVとかパワー半導体もEVにかかるとこですけども、時代を捉えたテーマで、研究者が書いていると読んでもらえるということが『研究技術計画』ではわかっています。
どういう立ち位置がいいのかは、このあたりがヒントになるのかなと思っています。私からの話題の話題提供は以上です。
〈質疑応答〉
Q1:若手研究者によるインタビュー機会
質問者1—理念に沿った記事では、実務家にインタビューする機会を若手研究者にすることで、なんとかならないものでしょうか?
吉岡—これはおっしゃる通りで、この実務家の記事も実は私がインタビューしています。インタビューして、私が起こして、それをお渡しして手直ししていただきました。私にとってもいい勉強になりました。クオリティを保つと同時に、やる側にとってもモチベーションなりますし、例えば博士課程の学生さんで、この分野の有名な方にお話聞きたいというのがあれば、インタビューをベースにしたご本人の記事という形にして書くこともあります。
質問者1—よくわかりました。経営学で実証分析などをやって、どんどん英文ジャーナルに論文を出さなきゃいけない若手も、いずれインタビューなどに基づいたところからいろいろ知見を得てまたというサイクルを作り出していけるようになってほしいなと、自分ができなかったことを若手に託して、若いうちにそういう経験をする機会を組織的に作れれば非常にいいことではないかなと思った次第です。
吉岡—ありがとうございます。経営学の今の必要事項を的確に捉えていらっしゃって、経営学の研究では、データをぶん回してこんな結果が出ましただけだと足りなくなってきているのが実態だと思うんですね。経営の中で本当にその問題を正しく捉えているのか、場合によっては定量分析と綿密な定性的調査を組み合わせた論文でないと評価されにくいこともありますので、若手にとって企業の中に入り込んでいくための機会として、これをうまく使うのはすごく大事だと思います。
Q2:オープンアクセス
質問者2—大学紀要の傾向として、リポジトリ搭載などバックナンバーのオープンアクセス化の動きがありますが、商業誌でもある貴誌でその種の知的アーカイブ化については検討されていますか。
吉岡—オープンアクセスはさすがに商業誌では難しいんですよね。東洋経済さんに入っていただいているので、買ってくださいとしか言えないのが実態です。ただ、裏をお話しすると、研究論文に関しては、東洋経済社さんから執筆原稿料をいただけるんですね。その原稿料をオープンアクセス料に充てることができるので、研究論文のオープンアクセスに間接的には繋がると思います。痛いところを突かれたなと思います。
原田—誰向けか、雑誌の傾向の問題だと思います。学術誌では、例えば年会費を払っている学会員以外でもすぐ見られるケースがあります。学会員のモチベーションに投稿したい、そしてそれを読んでもらいたいというのがある、つまりコストを負担する人に読んでもらいたいという思いがあるんでいいんですけど、商業誌、学術的な価値プラスアルファがある雑誌において、そういうモチベーションが機能しづらいのかなと思っています。
私自身の個人的な感想は、安すぎないかというのが一つ。一橋大学の先生方の知見に触れるのでも、理系だったら例えば材料を提供して良かったら共同研究の形で発表するけれど、『一橋ビジネスレビュー』を読んだ人が30万払うからケーススタディ買いますといった行動に移るかという問題を考えています。そのあたりは人文社会系の研究成果の繋がり方として難しいなとちょっと思います。
天野—オープンアクセス化について補足のコメントです。ハーバード大学は世界的にもオープンアクセスを主導してきた大学なんですけれども、ハーバードの中でもやっぱり『ハーバードビジネスレビュー』だけは別物の扱いだとオープンアクセスの担当者が言っていました。例えば京大でも、『法学論叢』は商業的なデータベースに載っていますので、そういうやり方もありなのかなと思っています。
吉岡—そうですね、『ハーバードビジネスレビュー』は相当バリューがあってかなりグローバルに売れているんですよね。『法学論叢』も、私はバックグランド法学なのでよくわかりますが、実務家は必ず買いますので。確かにあれは経済圏が成り立っていますから、わかります。
天野—オープンアクセスは進めないといけないけれど、別の方向に行くジャーナルがあってもいいかなと。
原田—学術発信やアウトリーチをやることには誰も反対しないんですけど、そのためのコスト、他の活動との兼ね合いだと思うんですね。誰がそれを負担するか、それを残すために何を犠牲にするかかなという気がしていますけど、それを何とか解決したいです。
私は『一橋ビジネスレビュー』読む方だと思っています。例えば『組織科学』は、私は読めないんですね、内容的に。研究者以外はたぶん読めないと思うんですね。日本の学会誌としては相当ハードル高い。そんな中で『一橋ビジネスレビュー』は読んでためになっていると思うし、『一橋ビジネスレビュー』を読んでいる自分に救われるところがあるんです。個人的には存続して欲しいんですけど、アウトリーチ活動が教員の人たちにどう評価されているのかなと思っています。アウトリーチ活動は研究活動とは違うけれど、社会に対して発信するが大学の本質的使命ならば、何らかの形で業績としてカウントしないとおかしいと思っています。
吉岡—業績評価で言うと、現状は一応評価されています。ただ、指定国立になってからは、やっぱ査読付き論文だよねというところがありまして、悩ましいんですね。
おっしゃったように、まさに学術誌で書いた論文、例えば自分が書いた論文をわかりやすく解説する、例えばこんな実務の話がありましたよと事例も交えて解説する立ち位置ですので、原田さんのような読者が増えると嬉しいなと思っています。
原田—ただ一方で、今の所属大学は評価するかもしれませんが、流動することを前提にしたときの個人への評価は別です。あるヨーロッパの大学が独自評価指標を作ったときに若手がすごく反対した。なぜかというと、ジョブマーケットの評価と自分の大学の評価が違うと困るからという話を聞いたことがあるんです。学問の多様性と言いながらダブルスタンダード的なところあるのかな、教員は悩んでいるんじゃないかなと勝手に思っています。
吉岡—その点は、『一橋ビジネスレビュー』に書くもう一つの動機としてありえることで、実は私立の大学へ行きたい方にはすごくいいんですね。アウトリーチなので、わかりやすく書けるかどうかが問われます。わかりやすく書いて、わかりやすく授業をしなくちゃいけないのは、比較的マスプロの授業をやっていらっしゃる大規模私立大学とか、あるいは比較的学力が高くない学生さんが行くような大学です。『一橋ビジネスレビュー』で書ける人っていいわけですよね。そこの就職活動にすごく使えるのではないかと思っています。
Q3:クオリティコントロール
質問者3—学術出版の方も多数参加されているので、メディアの違いと特性と分野特性について補足をした方がよいかと思ったので、コメントさせていただきます。
世界のグローバルスタンダードの学術誌に論文を出す競争には、補助線を1本引かなきゃいけない。いわゆる原著論文とレビュー論文です。若手の頃は原著論文を書いて一定のクオリティのもので戦って世界で示すことが必要なんですが、学会でのある一定の基準を満たしたら、レビュー論文を書いて引用されることも一つの業績競争になってきます。計量書誌学をやっていますと、一般にレビュー論文の方が引用数が多く、とくに社会科学で顕著ですが、一流誌のレビュー論文の引用数が圧倒的に高いことがあります。そこに書けること自体が一つのステイタスで、経営学は世界への標準化が進んでいる分野なので世界競争に準拠しているんですが、世界競争に入ってない社会学寄りになると、査読の付いていない依頼論文の方が偉いという国内誌のロジックも併存しています。さらに、法律学などでは、商業出版のエコシステムの中でレピュテーションシステムがあり、質の担保として、プロフェッショナルな編集者が介在することによって学術誌よりもクオリティが上がっている現実があるわけですよね。
それを一緒くたに指定国立になったから原著論文がよいとなって、補食ジャーナルなのかオープンアクセスジャーナルなのかよくわからないけど、インパクトファクターはついているところと、今まで日本国内で日本語の出版文化を維持してきたところとのバランスをどうとったらいいんだろうという状況が生まれてきていると思います。
吉岡先生は法律学からスタートしていてそのあたりの感覚も全部ご存知だと思うので、そういう違いもある中でどう考えているのかを聞かせていただけると助かります。
吉岡—おっしゃる通りで、法律ですと、裁判官の方、弁護士の方はプロですので、そういう方々が読んで、ある種ピアレビューよりも厳しい、読者としてボコボコに批判して、場合にはその人たちが自ら著者として乗り込んできて、こんな糞みたいなこと言ってるけどおかしいということがあり得て、そこでもまれるエコシステムがあります。
経営学も本来はそうあるべきだと思うんですね。経営学の中で、とくに実証研究ですと、本来はフィールドを持ってる方々(=産業界)が強いはずなんですよ。例えば、社員で実験しました、あるいはお客さんに対して実験しましたというと、より説得性が高いわけです。少なくともその顧客層の中では正しいんだということになります。私どもは商業誌としてうまく成り立っている面はあります。商業コミュニティの商業誌として出していて、商業コミュニティの中で十分にクオリティコントロールがなされていると思います。ここが、実務家の方にも求められている分野なのかどうかで、分かれてくるのかなと思いました。
でも、同じことが理系でも言えると思うんです。理系でも企業の研究者が多い分野ですと、商業ベースでも成り立ちうるんじゃないかなと思うんですけれども。それぞれの学術分野の違いもあるのかもしれませんが。
Q4:大学が出版機能を持つ意義
原田—大学出版さんも多く参加していますし、そもそも大学が出版機能を持つということについて、ぜひご意見をいただきたいですね。いろんな媒体があり、外部の雑誌もあるなか、大学が出版する意義があるとお考えでしょうか? 気軽に頼めるとか安いとかは別にして、大学が出版機能を持つ、大学がリードして発信することの現代的意義は大事かと思っています。紀要はたぶん今増えています。ハードルが下がったのかもしれません。ただ、経済学部とか、商学部とかわかりやすいんじゃなくて、学部が多様化して学問分類されていなくて、紀要も学問体系的でなくていろいろな研究が集まっている状況で、大学が出版機能を持つ意義って何なんだろうというのに、ぜひ吉岡さんのご意見をお願いします。
吉岡—他にいただいている質問「一つの方向性として、video abstractなどを取り入れてミスクトメディア的に展開する可能性もあったりするのでしょうか? 読者層的に」を混ぜながらお答えしたいと思います。
私の感覚からすると一番大事なのは、クオリティコントロールです。成果はリニアモデルじゃないと思うんですよ。リニアに出していくのは、原著論文で頑張りなさいと。ただ、原著論文もレビューアーとの創発なんですけどね、本当は。社会に問うていくんだったら、編集者や企画をする人たちとの創発性が必要です。一般書籍として売るんだったらなおさらそうだと思います。読者が何を求めているかを意識して書かないと、読んでもらえなくなってしまうので。大学が出版機能を持つことがいいのか悪いのかの本質は、そういう人たちを抱えられるかどうかによると思うんですね。法律分野のように、有斐閣さんという明確にそういう機能を持っている会社があるならもうそれでいいし、なければ自分たちで抱える必要あるかもしれない。そこが中心だと思います。
ただ、果たして出版だけなのかと。とくにビデオ・アブストラクト、映像でやったらいいんじゃないかと。大学教員だった方が、ご事情があって大学をお辞めになって、オンラインでビジネス研究を簡単に伝えるビデオを作ってらっしゃいます。そんなにたくさんの視聴者を抱えているわけではないんですけれども。YouTubeを使って無料で配信して、それを塾と結びつけて、そちらで収益性を担保されています。そういう形でアウトリーチするのも一つの手で、それも同じようにクオリティコントロールができるのであれば、それはそれで決して悪くはない。
出版機能を持つべきかは、悩ましいところがあります。ただし、繰り返しますが、私自身はプロフェッショナルな編集者の役割は相当大きいと思います。かなり鍛えられると。私自身もかなり鍛え上げていただいているので。その役割は捨てがたいんじゃないかな。
もちろんビデオの方も映像監督やプロデューサーの方々が入ることで、鍛えられるかもしれないなと思うんですけども、とりあえず映像よりは、論文を書く研究者としては、文字が書ける方がいいので、学術出版にまだ分があるかなって気はしています。
原田—上質な学術誌という言い方もあると思います。変な情報、悪貨が良貨を駆逐する、にはなってほしくないので、市場価値が少ないものでも発信していく機能をもし大学に担っていただけるならば、意義があると思います。一流の研究者が学術コミュニティだけで発信していると、変な社会科学の持論が普及しちゃうなと最近とくに心の中で感じています。
Q5:バーチャル特集等
質問者4—日本語である時点で教育的役割が重要で、かつ普遍性を重視することから、過去記事をまとめたバーチャル特集号等を組めると思います。その一部をオープンアクセス化してVisibilityをあげられればベターです。
吉岡—日本語なので、おっしゃる通りで、教育か社会に対して伝える役目があるのは当然そうです。日本語でわざわざやるならそっちが大事なわけですよね。過去記事をまとめたバーチャル特集号とか、例えば書籍に再編するとか、そういったことは大事だと思います。これは私どもの課題ですね。
Q6:プレゼン能力と文章力
質問者5—[教員として所属している]大学の教育においては、文章力もさることながら、制限時間内に手際よく資料を説明するプレゼン力や起承転結を持ったPPT資料作成能力が問われるように思います。文章力は確かに他のメディアに対するプレゼン力にも汎用されるかもしれませんが、そのあたりいかがでしょうか。なお、前職に在籍していた時に委託調査の報告書をスライドPDFで納品してくる業者(文章を書かないでプレゼン資料だけで報告書とする業者)が結構多くて、正直呆れました。現在における「文章力」とは何か、ということを考えさせられます。
吉岡—おっしゃる通りで、教育において学生さんに何を持って帰ってもらうかなんですけれども、非常に理解力の高い学生を除くと、体系を持ち帰るのは難しいんじゃないかなという肌感覚を持っています。ビジネススクールの方々においても同様です。ほとんどの方は「三つ大事な点を持って帰ってくださいね」の三つぐらいを持って帰ると。限られた方が、こういう因果関係のシステムなんだっていうことを持って帰るのがたぶん実態なんですね。
三つ大事なことの一つとして、わかりやすくて腑に落ちて、心を動かすようなプレゼン資料を作る技能が求められるのはそうだろうなと思います。
問題は、それをばっかりをやってしまうと、段々ロジカルに書けなくなって体系を書けなくなってくることだと思います。そこに因果関係が本当にあるかどうかの検証が必要なんですけれども、肌感覚としては段々書けなくなるよなと。キャッチーなことを言って、バラっバラっバラっと言って終わるんだろうなって思っています。
Q7:出版の見えにくいコスト
原田—出版のコストが下がっているのか、上がっているのか、わからないところあるんですけど、大学に関する出版には見えないコストが相当あると僕は思っています。その部分について考慮されないのが非常に問題だと思っているんですけど、なぜこういう問題起きるのか、そのあたり何かありますか? 2年前のこのセミナー参加された方に聞いたのですが、ある紀要はバーチャルの編集会でやっていたものを、労務管理の問題があるので部局の仕事にしたんですね。その結果、事務支援員さんの残業もなく、業務時間内に終わる内容でやっていると。バーチャルだと見えないこともあったのかなと思います。よく言えばボランタリーとか、血と汗とか、こういう経営的な問題はどうお考えでしょうか?
吉岡—おっしゃる通りで、『一橋ビジネスレビュー』でも担当する企画委員になって企画するときは、やっぱり時間がかかるわけですよ。私の担当のケースですと、だいたい100時間ちょっとかけました。
さらに、執筆者の方々がそれぞれ時間をかけているわけですよね。バーチャルでやってしまうと、なんとなくそれがかからない、コストが見えにくいっていうのは、それはもう本当その通りです。フィジカルにやった方がreturn on investmentが考えやすいというのはあります。