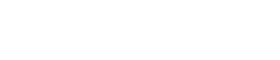《システム》としての学術コミュニケーション
学術情報流通に関する技術や議論が目まぐるしく進化・変化する中、そうした情報のアップデートは紀要編集者にとっての課題の一つとなっていると考えます。そこで、紀要編集者ネットワークでは、『学術コミュニケーション入門』を翻訳出版された宮入暢子様より、学術コミュニケーションの現状を知るうえで参考になる資料をまとめていただきました。
※ 本記事の引用に際しては、以下の記述をご利用ください。
宮入暢子. “《システム》としての学術コミュニケーション”. 紀要編集者ネットワーク. 2023-07-18. https://kiyo.cseas.kyoto-u.ac.jp/2023/07/nobuko-miyairi/, (参照 2023-07-18).
《システム》としての学術コミュニケーション
「学術コミュニケーション」を定義することは難しい。米国では、大学研究図書館協会(ACRL)が「学術コミュニケーション改革への理念と戦略 」と題した提言1の中で、以下のように位置付けている。
《システム》は制度や体系、秩序などと訳すことも可能だが、ここでは、さまざまなものが相互に作用する複雑な機構、あるいはそこに含まれる一連の原則、組織化された方法、といった意味も含め、敢えてそのまま《システム》としよう。この提言はACRLが2003年に「学術コミュニケーションイニシアチブ」を発足するにあたり発表したもので、《システム》の改革を奨励するとともに、大学図書館の関与を拡大することを目的としていた。学術出版物へのアクセス拡大、学術情報の公正価格、多様性と競争原理に基づく学術出版産業、価格高騰を回避しつつ流通を迅速化するための技術革新、査読による品質保証、著作権やフェアユース、長期保存の問題など、当時(そして現在でも)盛んに議論されていた課題について関係者の連携を促している。究極的には、より敏感に学術界のニーズに反応し、公共財としての学問研究の本質を反映する《システム》を目指した。
この《システム》は厄介なもので、研究分野によって少しずつ異なっている上に、その中で働く人々のほとんどが経験に基づく暗黙知に依存しているため、全体像を見渡す初心者向けガイドブックのようなものを作りにくい。例えば、研究者を目指す大学院生が、どの学会に参加し、どのジャーナルを読み、どのような業績を積み上げたらどのような評価を得るのか、といったことは、どこにも書かれていないか、仮にあったとしても特定の分野を念頭に置いたものであることが多い。さらに厄介なことに、近年この《システム》は技術的にも制度的にも革新が目覚しく、暗黙知にしろ形式知にしろ、その多くがすぐに陳腐化してしまう。
拙訳『学術コミュニケーション入門』2は、この《システム》についてざっくりとした知識を得るための入門書として極めて有用だと自負している。本書の目次には「査読とは何で、どのような仕組みなのか?」といった端的な疑問の数々が(あまり端的でないものも含めて)列挙されており、通読するにも、拾い読みするにも便利である。著者のリック・アンダーソンは米国の図書館に長く勤務する傍ら、出版業界も含め数々の団体の重職を歴任している。欧米の学術出版事情を背景とした著者の豊かな知識と洞察に、少しでも日本特有の事情を補うべく各章末に短い解説を追加したが、翻訳書として原著から大きく逸脱するわけにもいかず、最低限の補足にとどめた。絶妙な匙加減で《システム》の本質について広く浅くまとめた本書が、入門書としての役割を(少なくとも今後しばらくのあいだ)果たしてくれることを願う。
一方、《システム》の中ですでに仕事をしている研究者や実務家には、入門書を超えた知識を必要としている方々も多く、出版後に開催した輪読形式のウェビナーでは参考文献としていくつかの近刊書を紹介した。本稿ではそれらを中心に、学術コミュニケーションという《システム》の諸相について理解を深めるのに役立つ文献を紹介するとともに、関連ウェブサイト等についても言及する。『学術コミュニケーション入門』への補遺として、少しでも読者のお役に立てば幸いである。
学術出版産業とその市場
ACRLの定義によれば、学術コミュニケーションには「公式な」ものと「非公式な」ものの両方が含まれている。近年はプレプリントや研究データ、アカデミックSNSなども加わって《システム》の中身は多様化しているが、査読付きジャーナルや学術書が「公式な」学術コミュニケーションの筆頭であることは確かだ。「非公式な」学術コミュニケーションが全く認められないわけではないが、研究者としての評価を確立するためには「公式な」ものが不可欠だという構図は現在でも変わらない。アンダーソンは学術出版の役割について、「非公式」なものを「公式」なものにするための付加価値を提供するものとして位置付け、取捨選択、編集作業、発見可能性の向上(流通と検索)、ブランド化とマーケティング、の四つに分けて説明している。これらは研究者の能力とは異なる専門性と、人員配置や設備投資を必要とし、学術の発展と規模の拡大にしたがって産業として発展した。
しかし、産業としての学術出版が実際にどのように始まり、どれだけの利益をどのように上げているのかは、実際に論文や著書を出版している研究者にも、そしてそれらを収集し提供する図書館員にも案外知られていない。『学術出版の来た道』3は、学術出版の始まりから、主に学術ジャーナルやデータベース産業の発展について詳細に解説した類を見ない良書である。特に、(後にエルゼビア社が買収した)ペルガモン・プレスの創業者であるロバート・マクスウェルや、(インパクトファクターの生みの親として名高い)ISI社の創業者ユージーン・ガーフィールドに関する記述は、《システム》の変化によって生まれた潜在需要を見極めて時代の機運に乗じた「才気に長けた個人」のレガシーが、巨大な産業の一部となっていく様を描いており興味深い。また、オープンアクセスやビッグディール、行きすぎた定量評価への反対運動など、長く論争が続いている《システム》の重要な課題についてもコンパクトにまとめてあり、秀逸である。
STM協会は学術出版社や関連企業・団体を会員とする業界団体だが、その最新レポート4では、学術ジャーナルと学術書をあわせた市場規模は約140億ドルであると報告されている。データベースその他のツールや技術情報など関連領域を含めると、世界全体で約265億ドルである。学術出版社や文献データベースを提供する企業がこのように巨大な学術出版産業を築いて過剰な利益を上げていると批判する向きも多いが、学術界が「公式な」コミュニケーションを求め続け、それに応えようとする研究者がいる限り、この市場の拡大は止まない。パンデミックや戦争による影響も含め、経済の先行きが不透明なこの時代に、継続的な成長がほぼ確実に約束されている市場に営利を求める企業が群がるのは当然だろう。
筆者はコンサルタントという職業柄、学術出版市場の最新情報を常に追い続けているが、その情報源はこうした業界団体のレポートやホワイトペーパー、ブログ、ツイートなどが中心である。全てを巡回するのは時間がかかり見落としも多いため、メーリングリストやRSSフィードを利用してノートアプリ(現在はEvernoteを使用)に情報を蓄積し、まとめて読む。あるいは読まずに保存しておくだけでも、例えば「査読」について近年どのような新展開があったか調べようとする際、ノートアプリの中で「査読」「peer review」と全文検索するだけでかなりまとまった情報が取得できる。学術出版社が中心となって組織する国際専門団体 Society for Scholarly Publishing (SSP) がホストする The Scholarly Kitchenは、学術コミュニケーションに関わる最先端の知見を図書館や業界人の視点から提供しており、英語に抵抗のない方にはぜひお勧めしたい。国立国会図書館のカレントアウェアネス・ポータルは、The Scholarly Kitchenを含む内外の情報を日本語で紹介しており、筆者も頻繁に参照している。
学術書と大学出版
学術ジャーナルとともに「公式な」学術コミュニケーションの双璧を成す学術書について、筆者は実践に基づいた知識をもたない。これまでの勤務先が論文情報を中心に扱う職場であったためだが、『学術コミュニケーション入門』の翻訳にあたって日本の学術書の状況について概観しようとした際に、あらためて自身の経験不足を痛感した。前述のとおり、《システム》の実践は経験に基づく暗黙知に依存している。
あらためて学術書について学ぼうと手に取った数冊は学術書の編集者によるもので、その中でも『学術書の編集者』5はたいへん参考になった。速報性を重視し、同じジャーナルに掲載されてはいても内容的に独立した「情報」として流通するジャーナル論文に対して、学術書は体系的で全体的な「知識」であり、時にはそれを身につけたいという身体性をも重視して読者層を見極めつつ編まなければならないという視点には感銘を受けた。アンダーソンは学術書を読むことについてimmersiveという形容詞を使っているが、まさに身体性である。学術書の企画・編集における「審査」「査読」「ピアレビュー」と編集者が果たす役割は決してリニアなものではないとの図解を交えた解説や、出版助成の社会的効用など、実務経験に根差した知見のつまった貴重な一冊である。
続いて手に取った『学術書を書く』6と『学術書を読む』7の二冊も、学術書の編集に携わる実務家の手によるものだが、これらは学術書を出版しようとする研究者や、専門を超えて広く知識を得たい読者を対象としている。『わたしの学術書:博士論文書籍化をめぐって』8は、博士論文を書籍化することの意義やその過程を研究者の視点から描いており、「マラソンにたとえれば、前者は仲間内での記録会、後者は公式の大会」「やっと手にした名刺」といった表現の端々から、《システム》における学術書の意義を確認できる。
その他、日本の学術書事情について解説するにあたっては、大学出版部協会のウェブサイトから多くの示唆を得た。季刊誌『大学出版』は1986年の創刊号から全てがPDFで公開されており、翻訳作業を終えた後も少しずつ読み進めているところである。学術書のオープンアクセス化について、アンダーソンは欧米の大学出版局の取り組みや研究大学図書館を中心とする共同出資の事例を紹介している。日本の学術書出版は伝統的に公的助成によるところが大きいが、日本の大学出版が今後どのように展開するのか、大学図書館とはどう連携するのか、注視していきたい。
学術コミュニケーションの定量的評価
《システム》の中で行われるコミュニケーションに対する評価は、そのタイミングによって大きく二つに分けられる。学術コミュニケーションを「非公式」なものから「公式」なものにするために行われる評価と、公式・非公式にかかわらず世に出たものに対して行われる評価だ。前者はコミュニケーション自体の質や妥当性を問うもので、その判断ができる専門家によって行われる。後者の場合はそのような専門家が行う質的評価もあれば、確立された手順と方法論にしたがって行う(必ずしも内容の理解が伴わない)定量的評価もある。ビブリオメトリクス(計量書誌学)やサイエントメトリクス(科学計量学)は、そのような定量的評価によく使われる。筆者が計量書誌学データを扱う実務に携わってまもない頃、基本的知識を得ようと手に取った『研究評価・科学論のための科学計量学入門』9は、科学計量学の歴史や基本的な手法、研究評価への応用をわかりやすく説明した良書であった。
数値データは明快で、客観的で、科学的に思われるが、統計データであるがゆえに母集団や分布傾向を考えずに絶対的な評価値とすることにほとんど意味はなく、誤用や乱用につながりやすい。その最たるものがインパクトファクターである。これについては『科学を計る : ガーフィールドとインパクト・ファクター』10や『インパクトファクターを解き明かす』11といった著作のほか、数多くの論説や解説記事があって、そのほとんどが「インパクトファクターについて聞いたことはあってもよく知らない」読者を前提として、本来の意味や計算方法、どう使う(あるいは使わない)べきかを論じている。以下の近著二冊もその例に漏れないが、アプローチが大きく異なっているのでぜひ読み比べをされたい。
一昨年に刊行された『科学者をまどわす魔法の数字 / インパクト・ファクターの正体 : 誤用の悪影響と賢い使い方を考える』12には読みやすい文体と研究者ならではの視点に好感を抱いたが、内容は書名から想像したものとはかなり異なっていた。インパクトファクター自体の解説よりはずっと多くのページを「誤用と問題点」の指摘に費やしており、数々の計量書誌学分野の原著論文から引いた図表やグラフを根拠とした解説は、初めて引用データやその手法について触れる読者には参考になるだろう。ただし後段で「誤用がもたらすもの」として、撤回論文の増加や研究不正、再現性の危機などの原因をインパクトファクターに帰するのは飛躍しすぎであり、世界大学ランキングが「インパクトファクターが既に存在していたことで誕生した」との一文はあまりにも短絡的だ。インパクトファクターの誤用を戒めるEASE声明や研究評価に関するサンフランシスコ宣言を紹介して本書は唐突に終わる。つまり「賢い使い方」は、「使わない」ということか。書名から得る印象との矛盾はさておき、本書は引用データのクセを手っ取り早く理解した上で、インパクトファクター偏重主義に象徴される《システム》の歪みについて研究者の視点から理解するには役に立つだろう。
一方、『ジャーナル・インパクトファクターの基礎知識 : ライデン声明以降のJIF』13は、ISI社が1990年代後半に設立した日本オフィス(現在はクラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社)に最近まで在職していた著者によるもので、インパクトファクターの提供者側の視点に忠実に、かといって過度に擁護することなく、その基礎と実践に役立つ情報を伝えている。特に5章の「学術誌編集とジャーナル・インパクトファクター」では、学術ジャーナルの編集者が自誌にインパクトファクターを付与されるために具体的に何をしたらよいか、国内の事例も挙げて詳しく解説してあり、国内学会誌や紀要の国際化を目指す編集者には貴重な情報だろう。また、『科学をまどわす…』を含めインパクトファクター本の多くが陥りやすい誤用の指摘と批判だけにとどまらず、ライデン声明以降に生じた変化や提供側の対応などが示されている。
インパクトファクターは、学術コミュニケーションという《システム》の中で生まれた定量的評価指標の一つにすぎないが、その全体を象徴する曖昧なシンボルとして言及されることが多い。「科学技術動向」の2013年の掲載記事14は、《システム》の大半がオンラインに移行しつつある中、技術革新によって生じた学術コミュニケーションの定量的指標の多様化について、またそのような思想のもとに発案されたオルトメトリクスに関する初期の論考として貴重である。すでに十年以上が経過したが、いくつかの解説記事はあっても、オルトメトリクスに関するまとまった日本語の書籍はまだ見当たらない。
オープンアクセスとオープンサイエンス
オープンアクセスとオープンサイエンスは、この二十年あまりに《システム》の中で生じた最も大きな変化であり、いずれも現在進行形で関連文献は膨大な数に上る。ここでは筆者が個人的に特に影響を受けた資料について紹介するにとどめる。
アンダーソンは『学術コミュニケーション入門』の「オープンアクセスの機会と課題」と題した一章で、その背景や定義、OA出版モデルの種類などについてまとめている。セルフアーカイビングの思想とその受け皿としての機関リポジトリや図書館の役割に関連して、筆者も日本の状況について解説を加えたが、原著にSPARCに関する記述がほとんどないためSPARC Japanについては触れずじまいだった。2003年に「国際学術情報流通基盤整備事業」として開始されたSPARC Japanは、ジャーナル支援事業のみならず、大学図書館コミュニティを中心にオープンアクセス支援を拡大した重要なフォーラムである。そのウェブサイトには各種資料やニュースレター、SPARC Japanセミナーの講演資料などがアーカイブされており、日本におけるオープンアクセス運動の進捗とその時々の動向を理解するのに欠かせない第一級の資料群である。オープンアクセスについてSPARC Japanが発信する情報から多くを学んだのは、筆者だけではないだろう。
本家である米国のSPARCは、学術ジャーナルの価格高騰に端を発するシリアルズ・クライシスとビッグ・ディールへの懸念が強まる中、コミュニティ支援型のオープンアクセス誌の立ち上げを目指して1998年に発足した。米国の研究大学を中心とした会員団体で、運営コストも会費によって賄われている。2001年に発足したSPARC Europeは公益財団であるが、同様にメンバーシップ制をとっている。いずれも近年は大学図書館コミュニティが支援するオープンサイエンス関連イニシアチブの原動力となっており、オープンデータやオープンな教育への支援を拡大している。
オープンサイエンスはオープンアクセスを包含する概念として語られがちであるが、その原点は出版モデルではない。当初はWeb 2.0のアナロジーとしてのScience 2.0、つまり「インタラクティブな科学」として、ウィキやブログ、生データや初期段階のアイディアの共有など、技術革新が可能にした新しい研究実践を出発点としている。2014年にEUにより実施されたScience 2.0に関するパブリックコメント募集15の結果、「オープンサイエンス」や「オープンリサーチ」といった呼称がより好まれていることが明らかになり、この用語が広く定着していった。ウィキペディア英語版にopen scienceという項目ができたのは2006年、加筆が進んだのは2012年以降である。
筆者はちょうどその頃、マイケル・ニールセンの著書16のAudible版を入手し、通勤時間を利用して繰り返し聞いていた。日本では『オープンサイエンス革命』17という邦題で2013年に刊行されている。ネットワークが可能にする新しいサイエンスを、専門性や学術貢献の細分化、集合知によるスケールアップといった視点から豊富な事例とともに考察するニールセンの語り口はとてもエキサイティングだった。オープンサイエンスの促進には《システム》の文化変容が必須で、そのためには研究者よりもまず助成機関や評価者側からの革新を促していたのは先見の明である。実際、オープンサイエンスにおける政策的な取り組みは数多く、オープンサイエンス基盤研究センター(RCOS)のウェブページ18が国内外の政策動向について時系列でまとめているので参照されたい。オープンサイエンスの政策的なトップダウンは、オープンアクセスが学術出版、特に学術ジャーナルの価格高騰への対抗策として図書館を中心としたボトムアップな運動から始まっているのと対照的である。ただし、欧米ではオープンな学術情報基盤への資金提供を目指すSCOSSやInvest in Open Infrastructureといったイニシアチブを通じた大学図書館コミュニティによる資金提供が進められており、オープンアクセス運動からオープンサイエンス支援への連続性が感じられる。
日本におけるオープンサイエンスの進展については、月刊誌『科学』の2022年8月号に掲載されたオープンサイエンス特集19が役に立つ。日本を代表する論客がオープンサイエンスの諸相について論じており、コンパクトにまとまった理解を得るのに適している。また、近刊の『オープンサイエンスにまつわる論点:変革する学術コミュニケーション』20は情報科学技術協会の会誌の連載に新たに書き下ろし記事を加えて単行本化されたもので、ここ数年のオープンサイエンスの動向のみならず、変わりゆく《システム》の現在地を把握するのに極めて有用だ。
学術コミュニケーションの《エコシステム》
アンダーソンが頻繁に使う「学術コミュニケーションのエコシステム」という表現には、その内側で生産され流通するさまざまな学術情報の絶え間ない循環と、多くの異なる目的をもったステークホルダーが相互に依存している状況が込められている。もし我々が、《システム》の内側で肥大した学術出版産業を抑制し、公共財としての学術情報へのアクセスを保証しようとするのであれば、全体のバランスを崩さない程度に現実的な代替手段を確立しなければならない。そのためには、全てに精通する必要はなくとも、《システム》についてある程度の全体像を知っておく必要があるだろう。本稿がそのきっかけを提供できたとしたら幸甚である。
執筆者プロフィール
宮入暢子(みやいり のぶこ)
コンサルタント/アナリスト(学術コミュニケーション)
https://orcid.org/0000-0002-3229-5662
東京を拠点にフリーランスとして、STM出版や学術コミュニケーションに関わるコンサルティングに従事。その他、情報通信研究機構招聘専門員(2019-)、DataCite APAC Expert Group member(2020-)、筑波大学図書館情報メディア研究科非常勤講師(2019-2022)、青山学院大学コミュニティ人間科学部非常勤講師(2022-)など。過去にはORCID (http://orcid.org)のアジア・太平洋地区ディレクター(2015-2018)、ネイチャー・パブリッシング・グループ(現シュプリンガー・ネイチャー)のカスタム出版ディレクター(2012-2015)など。米国ハワイ大学マノア校図書館情報学修士。
1 “Principles and Strategies for the Reform of Scholarly Communication 1”. Association of College & Research Libraries (ACRL). https://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/principlesstrategies, (参照 2023-03-02).
2 Anderson Rick. 学術コミュニケーション入門 : 知っているようで知らない128の疑問. 宮入暢子訳. アドスリー; 丸善出版 (発売), 2022, x, 330p.
3 有田正規. 学術出版の来た道. 岩波書店, 2021, v, 148, 10p.
4 STM Global Brief – Economics & Market Size (An STM Report Supplement). International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers, 2021, 31p.
5 橘宗吾. 学術書の編集者. 慶應義塾大学出版会, 2016, vi, 198, 7p.
6 鈴木哲也, 高瀬桃子. 学術書を書く. 京都大学学術出版会, 2015, 155p.
7 鈴木哲也. 学術書を読む. 京都大学学術出版会, 2020, 138p.
8 春風社編集部. わたしの学術書 : 博士論文書籍化をめぐって. 春風社, 2022, 493, vi.
9 藤垣 裕子. 研究評価・科学論のための科学計量学入門. 丸善, 2004, x, 208p.
10 窪田輝蔵. 科学を計る : ガーフィールドとインパクト・ファクター. インターメディカル, 1996, 220p.
11 山崎茂明. インパクトファクターを解き明かす. 情報科学技術協会, 2004, 52p.
12 麻生一枝. 科学者をまどわす魔法の数字, インパクト・ファクターの正体 : 誤用の悪影響と賢い使い方を考える. 日本評論社, 2021, viii, 162p.
13 棚橋佳子. ジャーナル・インパクトファクターの基礎知識 : ライデン声明以降のJIF. 樹村房, 2022, ix, 147p
14 林和弘.「研究論文の影響度を測定する新しい動き:論文単位で即時かつ多面的な測定を可能とする Altmetrics」, 科学技術動向, No.134, pp.20-29, 2013. http://hdl.handle.net/11035/2357
15 “Science 2.0: science in transition”. Shaping Europe’s digital future. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/science-20-science-transition, (参照 2023-03-13).
16 Nielsen, Michael A. Reinventing discovery: the new era of networked science. Princeton University Press, 2012, 264 p.p.
17 Nielsen, Michael A. オープンサイエンス革命. 高橋洋訳. 紀伊國屋書店, 2013, 398p.
18 “オープンサイエンス政策動向|各種資料|国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター”. Nii.ac.jp. https://rcos.nii.ac.jp/document/policy/, (参照 2023-03-13).
19 岩波書店. 特集, オープンサイエンスをどう考えていくか. 科学. 2022, vol. 9, no. 8, p. 698-732.
20 南山 泰 之, 池内 有 為, 尾城 孝 一, 佐藤 翔, 林 和 弘, 林 豊, 情報科学技術協会. オープンサイエンスにまつわる論点 : 変革する学術コミュニケーション. 樹村房, 2023, vii, 168pp.