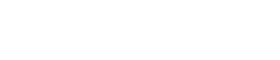【報告】研究・イノベーション学会第35回年次学術大会 実行委員企画セッション
研究・イノベーション学会第35回年次学術大会 実行委員企画セッション
公開セッション 「紀要の魅力と大学の役割」
(共催:紀要編集者ネットワーク)
日時: 2020年10月31日 18時−19時20分
(オンライン開催)
概要
国際的な指標による大学の研究力評価は、各教員の業績評価を競争的資金の獲得に加え、査読付国際ジャーナルへの掲載に急速にシフトさせた。一方でこのような動きは、掲載数重視につながり「掲載されやすい」テーマへの投稿を集中させる恐れもあり、それは研究(者)の多様性の維持に深刻な影響を与えている。このような状況下、扱うテーマ、ページ数、レイアウトが比較的自由な大学およびその所属部局が継続的に発行している紀要が再評価されている。
WEBサイト、SNSなど情報発信手段の多様化など大学及び研究者が急速に変化する現状、紀要の魅力と今後の展開、それを大学が担う意味を多様な参加者とディスカッションを行う。
企画趣旨
原田 隆(東京工業大学 情報理工学院 主任URA)
「紀要の魅力と大学の役割」
発表
報告者
高橋 愛典(近畿大学 経営学部 教授)
「私、紀要の味方です。-研究・イノベーション(学会)への貢献にむけて-」
資料
設楽 成実(京都大学 東南アジア地域研究研究所 助教)
「今、紀要に追い風が吹いている」資料
天野 絵里子(京都大学 学術研究支援室 リサーチ・アドミニストレーター)
「紀要の再発見」資料
ディスカッション
(当日の質疑応答の内容を、加筆・修正等のうえ公開いたします)
原 田:モデレーターとして、本セッションについて、大学経営という視点からコメントと提案をさせていただきます。
年次大会シンポジウムのテーマは「大学経営の現在と未来、大学の新たな役割と挑戦」でした。若手教員やURAが経営陣に対して質問をする形をとったパネルディスカッションも実施され、
若手教員から
- 社会は新しい役割を大学に期待し、大学執行部もそれらに答えようとする
- しかし、1つ1つの仕事を担当するスタッフ(若手教員が担当する事が多い)の負担が増え、「本来するべき」中核業務(教員の場合は研究と教育)にエフォートを割くことができない
というジレンマについて話をした後、経営陣にこれに対しての現状認識および対策について質問をする場面がありました。新しい活動を担当する部署が産学連携本部内、または部局横断的な(設置期限がある)組織として設立されるのですが、日々の活動の多くは若手教員や有期雇用職員が担当していることが多いのではないでしょうか。一方で若手教員のポジション獲得競争は激化の一途をたどっており、若手教員は様々な業務をこなしながら、なんとか時間を捻出し研究をしています。紀要に限定すると持ち回りで若手教員が編集委員として、原稿のとりまとめから発行、配送まで担当している大学がほとんどだと思います。
私は、この問題は大学経営、たとえばコスト―投入資金に加え、時間や担当するスタッフ数などもふくまれる―の観点から考察する必要があると考えています。
今回のセッションでは紀要を「大学の部局、または特定プロジェクトが継続して発行する学術誌」だと定義しました。「継続」して発刊されていることが重要です。悲しいことですが、紀要担当する教員の中には「やらされている」仕事と考えている人もいるでしょう。紀要の発刊には印刷費や郵送費などある程度の費用がかかります。継続するということに紀要の意義があるとすれば、財源が限られている中、紀要の発刊を続けることの意義を大学で働くすべての教職員にわかってもらわなければなりません。そのために何をするべきか。これは非常に重たい課題です。発表者の皆さんが指摘した紀要のもつすばらしい点について、おそらく参加された皆様も同意していただけたと思います。一方でそこに「お金をつけるか」、「人をつけるか」といった話になると、その実現は非常に難しいとも思われたと思います。
どうすれば「すべての」大学関係者に紀要の意義を認識してもらい、活動継続に必要となる経済的支援、スタッフの割当を決断してもらうことができるでしょうか。単に「紀要が必要だから」ということだけを訴えるのではなく、天野さんがおっしゃった大学のブランディング活動や情報発信の一環として紀要を位置づけ、将来の収益活動への展開や教育効果等を説明するなど波及効果までふくめて紀要を大切な経営資源として再定義することからはじめることが求められているのかもしれません。
大学にとって紀要は重要な資源であり活動であるなら、販売やクラウドファンディングなどの寄附等も学内関係部署と連携してすすめることもできるでしょう。紀要をアウトリーチ活動とみなすことができるのであれば紀要の発刊経費に寄附金をあてるなどの事例もでてくるかもしれません。
設 楽:私が先ほど話ししたことと絡みますと、大学が出版機能を持っていることの強み、利点について大学の再認識を促すことが非常に大事なことだと思います。図書館が紙版のジャーナルや電子ジャーナルの購読にどれぐらいコストがかかっていて、さらには、オープンアクセスジャーナルへの掲載料としてどれぐらいのお金が大学から出ているといった、お金の流れも見せながら、自分たち、つまり大学や研究者自身が出版機能を持っていることが、大学運営において強みであると考えるような議論があるといいと考えます。実際のところ、教員では電子ジャーナルの購読にいくらぐらいかかっているのか、といったことを、普段それほど意識していない方もいらっしゃるのでないかなと思います。
天 野:リソースの問題は、何をやるにしても問題になると思いますが、お金を持っている人に重要性を訴えて、意識を共有していくところからだと思います。大学でやるからには大学の執行部にわかっていただけるような文脈というのを持っていかないといけないと思いますが、既存の紀要というかたちでは、それがいいですよというはなかなか難しいのでないかなとは思います。ですので、申し上げたように全然別の文脈から大学の研究力を強化するというか、外部にはとらわれずに内部の多様な研究というのを生かして発信していくには、どういう効果的な方法があるか。それを考えた際に、紀要という形態というのが今までありましたという持っていき方もできると思います。さらに、今までの紀要ではだめで、発展させたこういった形態がありますという提案が可能かと思います。例えば、今日は時間がなくて全然紹介しきれないのですが、筑波大学が契約しているF1000Researchというサービスがあります。これは筑波大学の研究者が論文を投稿して、査読もされるというオンラインの論文プラットフォームになっています。分野を問わず、人文社会科学でもOK、言語も日本語でもOKというメディアにしていくとされていますので、「紀要」そのものではないですが、大学による新しい出版の形態としてこれから非常に注目される取り組みかなと思います。これは、URAが大学の執行部を説得して、資金調達もしたと聞いています。
髙 橋:リソースの件は、私が直接かかわるところでは、とにかく現状維持を大学当局にお願いするしかないというのが正直なところです。私自身、やはり助手の頃から紀要の編集をやってきたという経験が、教員になってから生かされたり、そうこうしているうちに査読の仕事が回ってきたり、学会誌の編集委員になったり、といった経験があります。あるいは自分たちで報告書や編著書を出すときにもいろいろ生かされると思います。これらは研究者としては結構基礎的なスキルで、アカデミックキャリアの早い段階である程度身につけておいたほうがよさそうです。これは研究・教育の本筋というよりも、いわゆる雑用・雑務の中に入る部分ではあるのですが、本来は教員や研究者の人材育成というときに、そういったものも含めてキャリアパスを考える姿勢も、本当は大学として持つ必要があるのかなと思います。ヒト・モノ・カネ・情報のうち、ヒトとカネの話だけになってしまいましたが、とりあえずここまでにして、続いてチャットでもいろいろご意見が出ているようですので、そちらを中心にディスカッションできればと思います。
質問者:学術情報の商業化が進む中において、大学が出版機能を持つことは非常に大事だということにおいては、品質保証という点において、分類といったものが大事になってくるということに対して、例えば、University Journalsではそのあたりをどう考えているのでしょうか。お話の中でプレプリントというワードは特に出てこなかったと思いますが、今、私が認識しているところだと、理系では要はプレプリントの機能に近いものが紀要と扱われているというか、それに近しいものだと思っていまして。ただ、プレプリントというのは分野の範疇の話ですので、それが紀要とはだいぶ違う、要は大学とか研究機関のインベントリとしての性質が紀要にあると捉えられるのでないかというのが思いました。プレプリントは今、商業出版社にどんどん取り込まれて、研究者はその上流の段階から全部出版社のほうに論文を投稿され、そこでAPCを取られ、最後はデータが全部そこに持ってかれるという状況にあるので、初め紀要できちんと押さえておくというのはとても重要であると考えます。ただ、紀要が重要だといっても、お金とかの問題もあるのですが、何がどこに載っているかよくわからないのでは紀要の使い勝手が悪すぎるので、それを改善するのが大事ではないかと思い、質問を書きました。特に、私も編集をやっていたことがあるのですが、そのカテゴリーが、何て言えばいいのですか、事例報告と書いてあるのだけれども書いてあるのはデータペーパーであったりとか、何がどこに載っているのかよくわからないというのがたくさんあるので、探すだけではなくて、査読者側も紀要だからいいかともうあきらめてしまうこともあるのですが、それを何とかきちんとしないと、その辺のもともとの元にいかないというので、ベストプラクティスなどあるのでしょうかというのがご質問です。
設 楽:University Journalsについてどう考えているかは、担当者に聞いてみます。(掲載論文のカテゴリーは、雑誌毎に位置づけが異なるものだと考えていましたので、私の方ではこうしたベストプラクティスについて考えたことがありませんでした。おそらく日本ではこのような議論は進んでいないと思います。実際、以前、投稿規定を色々調べてみたことがありましたが、カテゴリーの説明に就いて記載のない雑誌もありました。(追記))
質問者:紀要の名前を一旦捨てて再出発したらどうですか。大学からお金もらおうと思って、紀要で何かやりますよというよりは、別の名前でやったほうがお金取りやすいのではないかと考えます。
原 田:私は、紀要という名前にこだわる必要はないなとは思っております。
髙 橋:何か、名前変えてもすぐ正体が見透かされそうな気がしておりまして(笑)。今の状況を肯定しながら上を目指すほうがいいのかなと思います。特に老舗の大学ですと、第何十何巻というのが、非常に長く刊行し続けていること自体に意味があったりもします。それだけだとどんどん守旧的になっていってしまいますけれども、ただ名前を変える、新しい紀要を立ち上げることだけでも面倒ですし、、結局屋上屋を架すだけでかえって手間が増えますので、今までのものを簡単につぶせないような気もします。
設 楽:紀要には、一連の研究の段階的発表の場という機能もあるといわれています。こうした場合、ひとつの紀要に、掲載された自身の論文を引用しながら、順次、論文を発表してゆくことになります。現在、紀要の引用文献の公開は大手のジャーナルのように進んでいないと思いますが、今後紀要の引用文献の公開が進んでゆき、引用数といった点から紀要の評価が行われるようになると期待しています。こうした未来を考えるとき、名前をかえ新しい紀要を立ち上げることが不利なような気がします。
天 野:そうですね、確かにインパクトファクター的な考え方を前提とするとそうかもしれませんけれども、必ずしもそのジャーナル単位ではなくて論文単位でDOIがついていたら、ジャーナルの名前が変わるというところは必ずしもデメリットはないのかなと思います。
質問者:性格の違う問題を二つで申し訳ないのですが、実際にこの問題に突き当たっておりますので、ご意見を伺えればと思います。
一つは、紀要は部局が直営で出している場合もあるけれども、何々学会という外部団体の体裁を取っていることもあると思いますね。これが現在では組織運営上、労務管理上、財務管理上、問題になる場合もあるように思います。このことをこれから紀要を使っていくうえでどう考えたらいいかというのが一つの問題です。
二つ目は、人文社会系にあることですが、ダブルブラインドの必然性がないとすれば、誰が書いたかわかってもいいわけですよね。つまり、かつて人文系でよくあったように、一人称で論文を書くことが可能であり、例えば先行研究を引くときに、自分の論文は他人の論文と区別して、私はかつてこう書いたとか書いてよくなるわけですよね。そのことの功罪をどんなふうに考えたらいいかというのが人文社会系ではあると思います。
髙 橋:一つ目ですが、学内学会のことですよね。これがどういうかたちで始まったかというのは、私も調べようと思ったのですがよくわからなくて、多分、高等教育の歴史とか、そういうものをひもとく必要があると思います。学内学会が、それこそ学内の研究発表会を主催して、そこで研究報告することが昇格の条件になっているという大学も多々あると聞いております。一番の問題は、おカネだろうと思います。私が助手をしていた大学も「学会費」という名目で学生全員から毎年何千円かお金を徴収していて、それを助手が管理をしていたのですが、凄まじい貯蓄額になっていました。学生自治会費と一緒に徴収していて、自治会のほうは揉めたので、自治会費の自動徴収はなくなったのですが、その学内学会費はたぶんそのまま残ってしまっているのでないかと思います。だから、歴史をさかのぼると、ほとんどの大学で学内学会のかたちを取っていることに何かしらの経緯と理由があるのだと思うので、調べる必要があります。紀要の刊行費用は、本来は学費とかの収入から一括して大学が負担をすべきだと思いますし、今勤めている大学は、学内学会費は学生からはたぶん徴収していないと思いますので、大学によって差が結構あるのではないかと思います。単にばらばらですというだけでは、答えになっていなくて恐縮ですが。例えば、今お勤め先の大学で問題が起こっていることがあれば、差し支えのない範囲で教えていただけると大変助かります。
質問者:手短に申しますと、まず起源としては、私が所属先の場合は、ちゃんとした学会誌の体裁を取ろうと戦前に本当に思って、このようにしたという記録がありました。最初は大手出版社から発売されていたようです。それと二つ目のことですが、いろいろございます。要するに、URAの方の前であまり、言いにくいのですが、これは大学職員が業務としてやっているのか、別団体なのか、報酬は払っているのか、できあがった雑誌の所有権は誰にあり、それを大学が買い取っているとすれば対価は適正かとか、そういうことが当然起こりますし、お金が足りなくなるとまた大変ですし、増えすぎると、こんな任意団体の体制でこんな金額を扱っていいのかと、こうなると思います。
髙 橋:ありがとうございます。
原 田:査読は「業務か、それとも学外活動(ボランティア)か」はどの大学でも判断が難しく、大学経営を考える上でも大きな論点の1つです。
質問者:紀要の可能性は私も感じているところですが、紀要の投稿などを盛り上げてくためにはおそらく、現状どうしても、既存で横行してしまっているコミュニティごとの評価規範、例えば個人的にはあまり良いとは思わないのですが研究ランキングのようなものと、どうしてもバッティングしてくるところがあります。そこの部分をどう乗り越えていくのかというところが、やはり必要だろうと思いますね。もちろん私が今ここに解があるわけではないのですが、もし今回の登壇者の先生方で既にこういう課題にぶち当たっているとか、あるいは研究者側のそういう問題、規範の問題でなかなかそこが理解されないとかの実感のようなものがあれば、改めて追加で教えていただきたいなと思った次第です。よろしくお願いします。
髙 橋:紀要って結構いろいろな分野の教員が書いていますので、体裁からしてなかなか整わない場合もありますよね。法学の先生だけ縦書きなので反対側から開けるとか。質的なことを申せば、確かに自分が投稿した紀要のほかの論文を見たら、同僚の原稿ながら首を傾げるときもないわけではないのですが、そこはある程度寛容に受け止めていくしかなさそうです。それを多様性として面白いと見るのか、あるいは、外から見るとあまりにばらばらと感じられるのかというのは、本来は意識しておくべきことだと思います。先ほどカテゴリーの話も出ましたけれども、例えば「研究ノート」というカテゴリーは、何をもって研究ノートとするかという定義が投稿要領にもあまり書いていなかったり、分野によっても受け止め方が違ったりすることはあるので、その多様性を面白がりつつも、ルールとして整えるべきところあるだろうと思います。何か問題が起こってからではないと話が動きださないのかもしれませんけれども、そういうベストプラクティスみたいなものを共有し合うというのも、紀要編集者ネットワークのような横のつながりが充実してくると、面白くなってくるのかなとも思います。今日みたいな議論がいろいろなかたちで、全国各地でふつふつと起こってくると面白いなと。
原 田:それぞれの専門分野や組織に独自の価値基準があるのでしょうね。専門誌ではないがゆえの課題です。それを魅力と取るか、問題点と取るか。
天 野:私もこれは答えるのが難しいというか、もう永遠の課題だと思います。紀要を大事にしている分野の研究評価の規範と、対極にあるのがトップジャーナル重視で、トップジャーナルに出すことがやはり研究者として評価されてきた規範の中にいる研究者というのは、なかなかその部分ではわかり合えないのかなということを最近実感したことがありました。本当にそれは地道に変えていくという、お互いわかり合えるように、URAだったらURAが媒介していかないといけないのかなと思います。解はないのですが。
原 田:自分の読みたい紀要論文をコピーしていたときに、お目当ての論文の最後頁に隣の論文が写っている経験を皆様もお持ちだと思います。私はそれを読んだら面白かったことがよくありました。そのような経験が積み重なり紀要が好きなっていたと今は思います。専門誌とは違う編集ポリシーというか価値観に基づいたジャーナルがあってもいいのでないかというスタンスで、紀要を応援していきたいです。
原 田:この公開セッションは、数年ぐらい前に髙橋さんと個人的に紀要の話したことを端緒に、その後しばらくして紀要編集者ネットワークの存在知り、こういう活動に自分もかかわりたい、継続したいと思ったことがきっかけです。
今回のセッションが、紀要研究のプラットフォームを提供する活動につながればうれしいです。継続するためには、賛同者を広く集めるなどの課題があるのですが、ぜひ、皆さんのお力を借りながら実現したいと考えております。